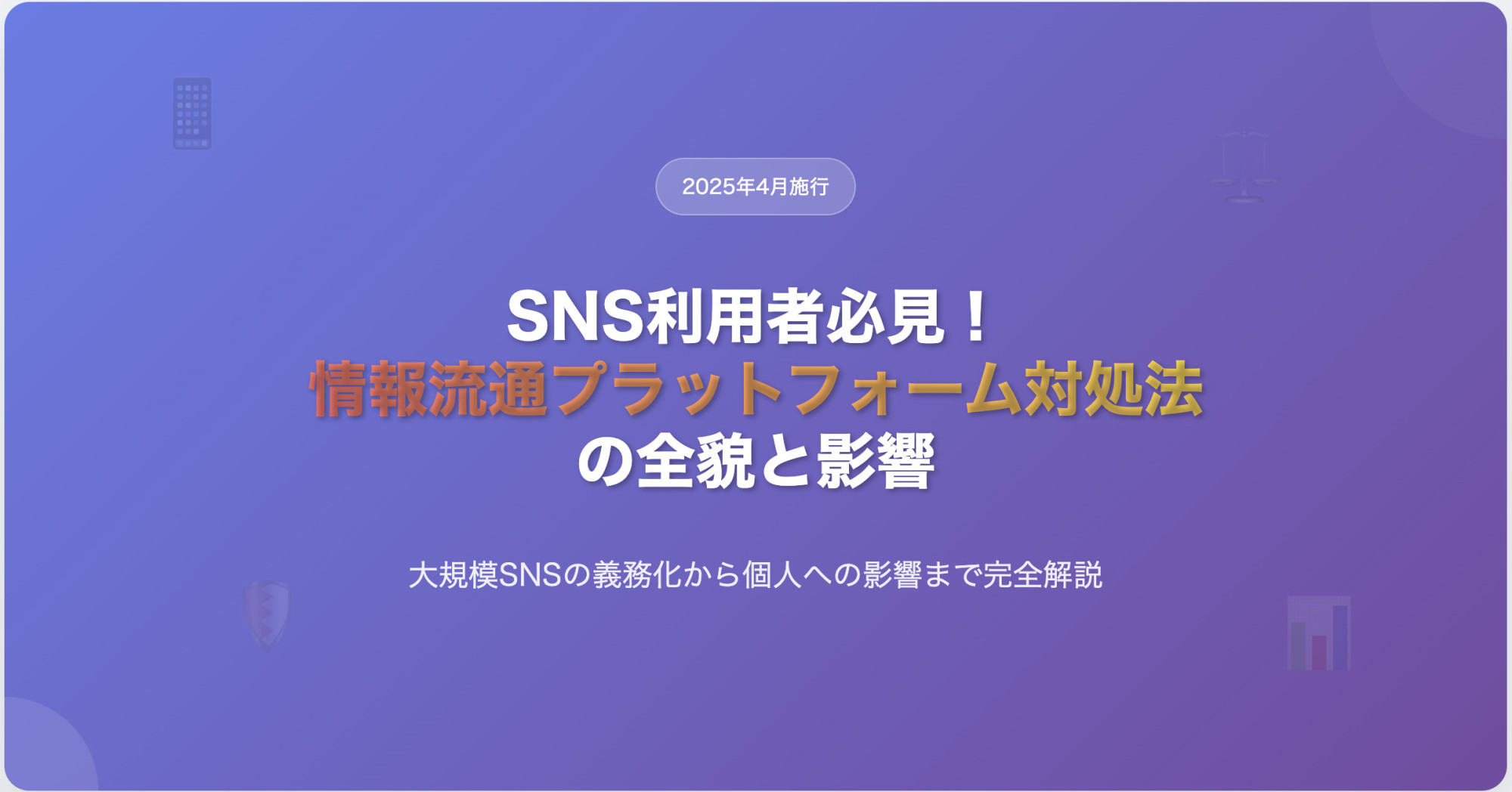目次
情報流通プラットフォーム対処法の概要
情報流通プラットフォーム対処法とは何か
情報流通プラットフォーム対処法は、2025年4月に施行された新しい法律で、SNSやインターネット上の大規模プラットフォームにおける権利侵害情報への対処を強化することを目的としています。本法律は、デジタル社会における権利侵害の発生を防止し、被害者への迅速な救済を提供するため、電気通信事業者を含む特定電気通信役務提供者に対して新たな義務を定めています。正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の改正法であり、従来のプロバイダ責任制限法を大幅に拡充したものです。
この法律により、大規模なプラットフォーム事業者には、誹謗中傷や権利侵害情報に対する迅速な対応が義務化されました。特に、月間アクティブユーザー数が1000万人を超える大規模プラットフォームサービスが主な対象となり、これらの事業者は権利侵害情報の通知を受けた場合、適切な措置を講じることが求められています。本法律の理解は、プラットフォーム運営者だけでなく、一般利用者にとっても重要なポイントとなります。
法改正の背景と目的
近年、SNSを中心とした情報流通プラットフォームにおいて、誹謗中傷や個人情報の無断公開、著作権侵害などの権利侵害情報の発生が急増しています。2022年から2024年にかけて、総務省が実施した調査によると、権利侵害に関する相談件数は年間平均約20万件に上り、特にSNS上での被害が深刻化していることが明らかになりました。これらの問題に対処するため、弁護士やサイバーセキュリティの専門家からは、法的枠組みの整備が急務であると指摘されていました。
従来のプロバイダ責任制限法では、権利侵害情報の削除や発信者情報の開示について、事業者の自主的な判断に委ねられている部分が多く、迅速な対応が困難な状況でした。このため、被害者の救済が遅れるケースが多発し、十分な実効性のある法的枠組みの整備が急務となっていました。特に、裁判手続きに関する複雑さが、一般人の権利救済を阻害する要因となっていました。
情報流通プラットフォーム対処法の施行により、大規模プラットフォーム事業者は、権利侵害情報の通知を受けた場合、一定期間内に適切な措置を講じることが法的義務となりました。本法律の策定により、被害者の迅速な救済と、健全な情報流通環境の実現を目指しています。2025年5月以降、本格的な運用が開始される予定となっており、各事業者は対応体制の構築を進めています。
情報流通プラットフォーム対処法の具体的な内容
権利侵害情報の通報手続き
情報流通プラットフォーム対処法では、権利侵害情報の通報手続きが大幅に簡素化されました。被害者は、各プラットフォームが提供する専用のフォームを通じて、権利侵害の内容、根拠となる法的権利、具体的な被害状況を記載して通報することができます。この手続きの簡素化により、一般の人でも容易に権利侵害の通報が可能となり、サイト運営者による迅速な対応が期待されています。
通報可能な権利侵害情報の種類
| 権利侵害の種類 | 内容 |
|---|---|
| 名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害 | 個人の名誉や人格を傷つける投稿 |
| 知的財産権侵害 | 著作権、商標権、肖像権などの侵害 |
| 個人情報の無断公開 | 氏名、住所、電話番号等の無断掲載 |
| 業務妨害 | 虚偽情報の流布による業務への支障 |
通報処理のタイムライン
| 段階 | 期限 | 内容 | 責任者 |
|---|---|---|---|
| 受付確認 | 24時間以内 | 通報内容の受領確認を実施 | 指定された担当者 |
| 初期判断 | 7日以内 | 権利侵害の可能性について判断 | 審査委員会 |
通報を受けたプラットフォーム事業者は、上記のタイムラインに従って迅速な対応を行うことが義務付けられています。この迅速な対応により、権利侵害情報の拡散を早期に防止することが可能となります。また、各事業者は専門のセンターを設置し、24時間体制での受付を行う方法を採用しています。
削除義務とその手続き
大規模プラットフォーム事業者は、権利侵害情報の通報を受けた場合、以下の手続きに従って削除措置を実施する義務があります。本法律では、第12条に基づいて削除手続きの詳細な方法が定められており、各事業者は統一的な対応が求められています。
削除措置の手続きフロー
| 段階 | 期間 | 内容 | 変更点 |
|---|---|---|---|
| 初期審査 | 通報受付後即時 | 通報内容の形式的要件を確認し、権利侵害の可能性を判断 | 従前より迅速化 |
| 発信者への通知 | 初期審査後即時 | 権利侵害情報の発信者に対して、削除要請があった旨を通知 | 通知方法の標準化 |
| 反論期間の設定 | 通知後 | 発信者に対して、7日間の反論期間を設定 | 期間を明確化 |
| 最終判断 | 反論期間終了後 | 反論内容を踏まえて、削除の可否を最終判断 | 審査員による客観的判断 |
| 措置の実施 | 最終判断後即時 | 削除が適切と判断された場合、速やかに削除措置を実施 | 結果の通知を追加 |
削除措置の実施にあたっては、表現の自由との調和を図るため、透明性レポートの公表が義務付けられています。事業者は、削除要請の件数、削除実施件数、削除理由の分類などを四半期ごとに公表することが求められています。これらの情報は、各事業者の公式サイトでの表示が義務付けられており、利用者が容易にアクセスできるようになっています。

発信者情報の開示請求
情報流通プラットフォーム対処法では、発信者情報の開示請求手続きも大幅に改善されました。従来は裁判所での手続きが必要でしたが、新法では事業者への直接請求が可能となり、より迅速な情報開示が実現されています。この変更により、申請者は複雑な裁判手続きを経ることなく、直接的な方法で発信者情報の開示を求めることができるようになりました。
開示請求可能な発信者情報
| 情報の種類 | 具体的な内容 | 開示条件 |
|---|---|---|
| 通信記録 | IPアドレス、ポート番号、タイムスタンプ | 権利侵害の発生が明確 |
| 個人情報 | 発信者の氏名、住所、電話番号 | 申請者の権利が明確 |
| 連絡先情報 | 電子メールアドレス | 送信者の特定が可能 |
| アカウント情報 | ユーザーID、登録情報等 | 一部の情報は除外有 |
開示請求を行う場合、被害者は権利侵害の事実を疎明する必要があり、事業者は請求内容を審査した上で、適切と判断される場合に限り情報開示を実施します。この手続きにより、匿名性を悪用した権利侵害行為に対する実効的な対策が可能となります。申請時には、弁護士による代理申請も可能となっており、専門的な支援を受けることができます。
対象となる事業者とその義務
大規模プラットフォーム事業者の定義
情報流通プラットフォーム対処法における大規模プラットフォーム事業者の定義は、以下の要件を満たす事業者とされています。本法律では、第3条において事業者の指定基準が明確に定められており、総務省が定める基準に基づいて指定が行われます。
大規模プラットフォーム事業者の要件
| 要件 | 基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 利用者数要件 | 月間アクティブユーザー数が1000万人以上 | 日本国内の利用者数 |
| サービス範囲 | 日本国内でサービスを提供している | 日本語サイトの提供 |
| 機能要件 | ユーザー間の情報交換、情報発信機能を有する | 送信機能を含む |
| 影響度要件 | 社会的影響力が大きいと総務省が認定 | 定期的な見直し予定 |
これらの要件により、主要なSNSプラットフォーム、動画共有サービス、ブログサービス、電子掲示板などが対象となります。具体的には、X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、LINE、ニコニコ動画などの大手プラットフォームが該当します。各事業者は、指定を受けた場合、総務省への届出と対応体制の整備が義務付けられています。
中小規模の事業者については、従来のプロバイダ責任制限法の枠組みが適用されますが、情報流通プラットフォーム対処法のガイドラインを参考にした自主的な取り組みが推奨されています。また、将来的には利用者数の変更に応じて、指定事業者の一覧が更新される予定となっています。
義務化された対応策
大規模プラットフォーム事業者に義務化された対応策は、以下の通りです:
義務化された対応策の詳細
| 分野 | 具体的な対応策 | 実施期限 |
|---|---|---|
| 透明性の確保 | ・利用規約、コミュニティガイドラインの明確化・権利侵害情報の削除基準の公表・透明性レポートの定期的な公表 | 2025年5月まで |
| 迅速な対応体制の構築 | ・権利侵害情報の通報受付窓口の設置・24時間以内の受付確認体制・7日以内の初期判断実施体制 | 既に義務化済み |
| 技術的措置の導入 | ・自動検知システムの導入・改善・繰り返し違反者への対応強化・本人確認システムの導入検討 | 段階的実施 |
| 組織体制の整備 | ・専門チームの設置・外部専門家との連携体制・定期的な研修・教育の実施 | 継続的対応 |
これらの対応策により、プラットフォーム事業者は権利侵害情報への迅速かつ適切な対応が可能となり、利用者の権利保護と表現の自由の調和を図ることが期待されています。各事業者は、専門の審査員を選任し、十分な体制を構築することが求められています。

情報流通プラットフォーム対処法に違反した場合のリスク
違反に対する罰則
情報流通プラットフォーム対処法に違反した場合、事業者には以下のような罰則が科せられる可能性があります。本法律では、違反の態様に応じて段階的な処分が定められており、最終的には業務停止命令まで発出される可能性があります。
違反に対する罰則体系
| 罰則の種類 | 内容 | 発令機関 |
|---|---|---|
| 行政処分 | ・総務省による改善命令の発出・業務停止命令(重大な違反の場合)・公表措置による社会的制裁 | 総務省 |
| 刑事罰 | ・法人に対する罰金刑(最大1億円)・担当者個人への刑事責任追及・業務上過失致死傷罪の適用可能性 | 検察庁 |
| 民事責任 | ・被害者からの損害賠償請求・集団訴訟のリスク・取引先との契約解除リスク | 民事訴訟 |
違反の程度や頻度、改善意欲の有無などが総合的に判断され、段階的な処分が実施されます。初回違反の場合は警告や指導が中心となりますが、繰り返し違反や悪質な違反の場合は、より重い処分が科せられる可能性があります。
事業者が負うリスク
情報流通プラットフォーム対処法への対応が不十分な場合、事業者は以下のような多面的なリスクに直面します:
事業者が負うリスクの分類
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 法的リスク | ・行政処分による事業継続への影響・被害者からの損害賠償請求の増加・株主代表訴訟のリスク |
| 経済的リスク | ・罰金や損害賠償による直接的な経済損失・対応体制構築に伴う大幅なコスト増加・広告収入の減少や利用者離れによる収益悪化 |
| 社会的リスク | ・企業イメージの悪化・利用者の信頼失墜・人材確保の困難化 |
これらのリスクを回避するため、事業者は法令遵守体制の構築と継続的な改善が不可欠となります。特に、権利侵害情報への迅速な対応と透明性の確保は、社会的信頼の維持において重要な要素となっています。
他の法令との関連性
個人情報保護法との関係
情報流通プラットフォーム対処法は、個人情報保護法との密接な関連性を有しています。特に、発信者情報の開示請求においては、個人情報保護法の規定との整合性を図る必要があります。
発信者情報の開示は、発信者の個人情報の第三者提供に該当するため、個人情報保護法の例外規定(法令に基づく場合、本人の同意がある場合等)に該当することが必要です。情報流通プラットフォーム対処法では、権利侵害情報の削除や発信者情報の開示が法令に基づく処理として位置付けられており、個人情報保護法との調和が図られています。
また、プラットフォーム事業者は、利用者の個人情報を適切に管理し、不正アクセスや情報漏洩の防止に努める必要があります。これらの取り組みは、情報流通プラットフォーム対処法における信頼性の確保と密接に関連しています。
電気通信事業法との関連
情報流通プラットフォーム対処法は、電気通信事業法の特別法的な位置付けを有しており、電気通信役務の提供に関する規制との整合性が図られています。
電気通信事業法では、通信の秘密の保護が基本原則として規定されていますが、情報流通プラットフォーム対処法では、権利侵害情報への対処という公益的な目的のため、一定の条件下で通信の秘密の制約が認められています。
また、電気通信事業法における利用者保護の観点から、プラットフォーム事業者は利用者への適切な情報提供と、公正な取り扱いが求められています。これらの要請は、情報流通プラットフォーム対処法における透明性の確保と連動しています。
独占禁止法との関連
大規模プラットフォーム事業者の市場における影響力を考慮し、情報流通プラットフォーム対処法は独占禁止法との関連性も有しています。
プラットフォーム事業者が権利侵害情報の削除や発信者情報の開示を行う際、競合他社や特定の利用者を不当に排除することは、独占禁止法上の問題となる可能性があります。このため、削除や開示の基準は公正かつ透明でなければならず、恣意的な運用は禁止されています。
また、大規模プラットフォーム事業者に対する規制強化は、市場の競争環境にも影響を与える可能性があります。新規参入事業者との公平な競争を確保するため、規制の内容や適用範囲については、継続的な検討が必要とされています。
国際的な法規制との比較
EUのデジタルサービス法(DSA)との比較
EUのデジタルサービス法(Digital Services Act: DSA)は、2024年2月に施行された法律で、情報流通プラットフォーム対処法と多くの共通点を有しています。
日本法とEU DSAの比較
| 項目 | 日本(情報流通プラットフォーム対処法) | EU(デジタルサービス法:DSA) |
|---|---|---|
| 対象基準 | 月間アクティブユーザー1000万人以上 | 月間アクティブユーザー4500万人以上 |
| 透明性レポート | 義務化 | 義務化 |
| 違法コンテンツ削除 | 迅速な削除義務 | 迅速な削除義務 |
| 利用者保護 | 権利保護の強化 | 権利保護の強化 |
| 特別規定 | 発信者情報の開示に重点 | システミックリスクの評価・軽減義務 |
これらの比較から、日本の情報流通プラットフォーム対処法は、EUのDSAと類似した方向性を持ちながらも、日本の法制度や社会情勢に適した独自の特徴を有していることがわかります。
米国のセクション230条との違い
米国の通信品位法セクション230条は、プラットフォーム事業者に対して幅広い免責を認めており、情報流通プラットフォーム対処法とは大きく異なるアプローチを取っています。
米国セクション230条と日本法の比較
| 項目 | 米国(セクション230条) | 日本(情報流通プラットフォーム対処法) |
|---|---|---|
| 基本方針 | プラットフォーム事業者の免責を幅広く認める | 事業者の積極的な対応義務を規定 |
| 削除対応 | 自主的な削除に対する保護を規定 | 透明性の確保と説明責任を重視 |
| 優先価値 | 表現の自由を最大限に尊重 | 被害者の救済を優先的に考慮 |
これらの違いは、各国の法制度、文化、社会的価値観の違いを反映しており、グローバルなプラットフォーム事業者にとっては、各国の法規制に適応した対応が求められています。
情報流通プラットフォーム対処法がもたらす影響
情報流通プラットフォーム対処法の施行により、インターネット上の情報流通環境は大きく変化することが予想されます。利用者、事業者、社会全体にとって、以下のような影響が考えられます。
各ステークホルダーへの影響
| 対象 | 影響の内容 |
|---|---|
| 利用者 | ・権利侵害情報に対する迅速な救済の実現・安全で健全な情報環境の構築・表現の自由に対する一定の制約 |
| 事業者 | ・対応コストの増加と体制整備の必要性・新たなビジネスチャンスの創出・競争環境の変化 |
| 社会全体 | ・デジタル社会の信頼性向上・国際的な競争力の強化・法制度の継続的な改善 |
電子契約・電子署名サービスとの関連性
情報流通プラットフォーム対処法の施行により、企業や個人の情報管理に対する意識が高まる中、電子契約・電子署名サービスの重要性がより一層注目されています。
特に、権利侵害情報の発信者情報開示請求や削除要請において、真正な権利者であることを証明する必要があり、電子署名技術による本人確認や文書の真正性担保が重要な役割を果たします。
まとめ
情報流通プラットフォーム対処法は、デジタル社会における権利保護と表現の自由のバランスを図る重要な法律として、2025年4月に施行されました。大規模プラットフォーム事業者には新たな義務が課せられ、利用者には迅速な救済の道が開かれています。
この法律の施行により、インターネット上の情報流通環境はより健全で信頼性の高いものになることが期待されますが、同時に事業者や利用者には新たな対応が求められます。
電子署名技術を活用したソリューションは、この新しい法的環境において重要な役割を果たし、特にONEデジシリーズのような包括的なソリューションは、法令対応と業務効率化を両立する有効な手段となるでしょう。
情報流通プラットフォーム対処法の適切な運用により、デジタル社会の信頼性向上と、すべての利用者にとって安全で健全な情報環境の実現が期待されます。
参考サイト
総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html
情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会
https://www.isplaw.jp/
参考文献
リーテックス株式会社
河原淳平特別顧問インタビュー「SNS・AIにおける本人確認の必要性」
https://le-techs.com/content/blog/kawahara-interview04