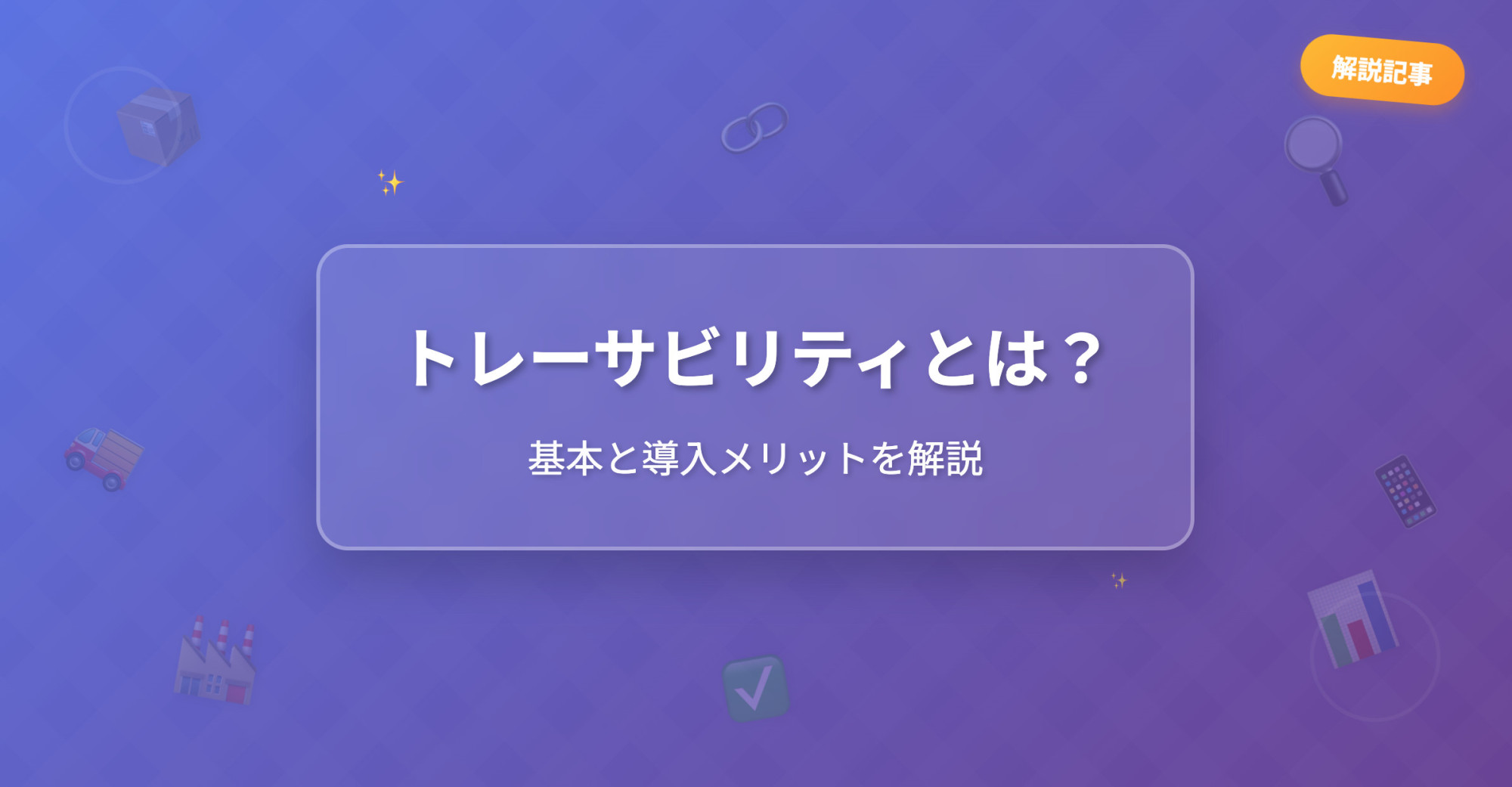近年、製造業や流通業界において「トレーサビリティ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。食品の安全性確保、製造工程の品質管理、さらには環境配慮や社会的責任といったESG経営の観点からも、トレーサビリティの重要性は高まり続けています。
本記事では、トレーサビリティの基礎知識から導入によるメリット、実際の活用事例、そして未来の展望まで、企業が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。
目次
トレーサビリティとは何か
トレーサビリティの定義と意味
トレーサビリティ(Traceability)とは、日本語で「追跡可能性」を意味し、製品やサービスの生産から流通、消費に至るまでの履歴を追跡できる仕組みのことを指します。
具体的には、原材料の調達段階から製造工程、出荷、販売、そして最終的に消費者の手に渡るまで、各段階における情報を記録・管理し、いつでも遡って確認できる状態を実現する管理手法です。国際標準化機構(ISO)では、「考慮の対象となっているものの履歴、適用又は所在を追跡できること」と定義されています。
製品追跡システムによって、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのように」製造・加工・流通させたのかという5W1Hの情報が明確になり、製品の品質保証や安全性確保に大きく貢献します。

トレーサビリティの必要性
現代社会において、トレーサビリティの必要性が高まっている背景には、複数の重要な要因があります。
第一に、消費者の安全意識の高まりです。食品偽装問題や製品リコールなどが発生するたびに、消費者は製品の安全性や出自を確認したいというニーズを強めています。
第二に、グローバル化に伴うサプライチェーンの複雑化です。複数の国から原材料を調達し、複数の拠点で製造・加工を行う現代の製造業において、問題発生時に原因を特定するには、各段階の情報を正確に把握できる体制が求められます。
第三に、法規制への対応があります。食品衛生法や医薬品医療機器等法など、業界ごとに製品の追跡可能性に関する法的要件が定められており、これらの規制に対応するためにトレーサビリティシステムの導入が求められています。
第四に、ESGやサステナビリティへの関心の高まりです。環境負荷の低減、人権尊重、倫理的な調達など、企業の社会的責任が問われる中、調達から販売までの流れを可視化する手段としてトレーサビリティが重視されています。
トレーサビリティの技術的側面
ブロックチェーン技術の役割
製品追跡システムの構築において、近年特に注目されているのがブロックチェーン技術です。
ブロックチェーンは、取引記録を分散型台帳として管理する技術であり、データの改ざんが極めて困難という特徴を持ちます。従来の中央集権型データベースと異なり、サプライチェーンに関わる全ての参加者が同じ情報を共有し、かつその情報の真正性を担保できるようになります。
例えば、食品業界では、農場での生産情報から加工工程、流通経路、小売店での販売まで、全ての情報をブロックチェーン上に記録することで、購入者がモバイル端末でQRコードをスキャンすれば、その食品の履歴を確認できるシステムが実用化されています。

ICタグとロット管理の関係
効果的な追跡システムを構築するには、製品や原材料を個別または単位ごとに識別・追跡する技術が必要です。その中核を担うのが、ICタグ(RFIDタグ)とロット管理の仕組みです。
ICタグは、電波を使って非接触でデータの読み書きができるデバイスで、一度に複数のタグを読み取れること、汚れや破損に強いこと、より多くの情報を記録できることなど、バーコードと比較して多くの優位性があります。
ロット管理は、製品を製造単位や時間単位でグループ化し、グループごとに管理する手法です。万が一問題が発生した場合に、影響範囲を特定し、該当するロットだけを迅速に回収できます。ICタグとロット管理を組み合わせることで、個別レベルからロットレベルまで、柔軟な粒度で製品追跡を実現できます。
追跡管理システムがもたらす3つの利点

歩留まり向上と不良品の流出防止
製品追跡システムの採用は、製造業における歩留まり(製造効率)の向上に直接的に貢献します。
各製造工程でデータを収集・分析することで、どの工程で、なぜ不良品が発生しているのかを正確に把握できます。特定の原材料ロットや製造装置、作業時間帯に不良率が高いといった傾向が見えれば、その原因に対して的確な改善策を講じることができます。
また、万が一不良品が市場に流出した場合でも、該当するロットや製造日時を即座に特定し、必要最小限の範囲で製品を回収できます。すべての製品を回収する必要がなく、問題のある特定のロットだけを対象とすることで、企業の経済的損失を大幅に削減できます。
リスク管理とブランドイメージの向上
現代のビジネス環境において、リスク管理は企業存続の鍵を握る重要な経営課題です。製品追跡システムは、様々なリスクへの有効な対策として機能します。
製品の品質問題や安全性の問題は、一度発生すると企業のブランドイメージに深刻なダメージを与えます。一方、追跡管理の仕組みを整備していれば、問題発生時に迅速かつ正確な情報開示ができ、企業の透明性と誠実さをステークホルダーに示すことができます。
また、追跡情報の開示はブランド価値を向上させる重要な要素にもなります。製品の生産地や製造プロセスを詳細に説明できることは、品質への自信の表れです。特に、オーガニック食品や高級ブランド品では、追跡情報を積極的に開示することで、製品の正当性や付加価値を証明し、ブランドの信頼性を高めています。
さらに、ESGやサステナビリティの観点からのリスク管理も重要です。サプライチェーンにおける人権侵害や環境破壊を早期に発見し、対処できます。
顧客対応の効率化と信頼関係強化
製品追跡システムは、顧客管理業務の効率化にも大きな効果を発揮します。
製造業や流通業では、顧客企業から製品の仕様や納品履歴に関する問い合わせを頻繁に受けます。追跡管理の仕組みを導入していれば、「いつ、どのロットの製品を納品したか」「使用された原材料は何か」といった情報を瞬時に検索でき、顧客対応の時間とコストを大幅に削減できます。
また、製品の追跡データを顧客と共有することで、供給網における情報の可視性が高まり、顧客との信頼関係が強化されます。
トレーサビリティの実際の事例
BSE問題とトレーサビリティの関係
トレーサビリティの重要性を世界に知らしめた代表的な事例が、2000年代初頭に発生したBSE(牛海綿状脳症)問題です。
日本では2001年に国内初のBSE感染牛が確認され、消費者の牛肉離れが急速に進みました。この危機的状況において最も問題となったのが、どの牛肉がどこから来たのかを追跡できないことでした。
この経験を踏まえ、日本政府は2003年に「牛トレーサビリティ法」を制定しました。この法律により、国内で飼養されるすべての牛に個体識別番号が付与され、出生から屠畜、流通、販売に至るまでの情報が一元管理されるようになりました。
現在では、スーパーマーケットや飲食店で販売される牛肉には個体識別番号が表示され、消費者はウェブサイトでその番号を入力するだけで、牛の品種、生年月日、出生地、飼養履歴などの詳細情報を確認できます。
食品業界におけるトレーサビリティの実践
BSE問題以降、食品分野における追跡管理の導入が急速に進展しました。
大手食品メーカーでは、原材料の調達から製品の販売まで、すべての工程をデジタル化し、リアルタイムで追跡できるシステムを導入しています。農産物であれば生産者や栽培方法、加工食品であれば使用した原材料のロット番号や製造日時などを管理します。
近年では、商品に印刷されたQRコードをモバイル端末でスキャンすると詳細情報にアクセスできるサービスも充実してきました。産地の写真や生産者のメッセージ、栄養成分の詳細などを確認でき、消費者は安心して製品を選択できます。
医薬品業界におけるトレーサビリティの実践
医薬品業界は、人命に直結する製品を扱うため、最も厳格なトレーサビリティが求められる分野の一つです。
日本では、薬機法により医薬品の製造から流通、使用に至るまでの記録保管が義務付けられています。医療用医薬品には商品コードや製造番号を含むバーコードが表示され、医療機関では調剤時や投薬時にこれを読み取ることで、患者への誤投薬を防止しています。
また、偽造医薬品の流通防止も重要な役割です。欧州連合(EU)では2019年から医薬品の包装に固有の識別コードと改ざん防止装置を付けることが義務化され、偽造品の混入を検知できるようになっています。
トレーサビリティ導入の課題と未来
追跡システム実装における障壁
製品追跡管理の導入には、依然として様々な課題が存在します。
第一の課題は、初期投資とランニングコストです。ICタグやバーコードリーダーなどのハードウェア、データ管理システムなどのソフトウェア、システム運用のための人材育成など、相当な投資が必要です。
第二の課題は、供給網における協力体制の構築です。原材料の生産者から最終消費者まで、関わる全ての参加者が情報を記録・共有して初めて効果を発揮します。
第三の課題は、データの標準化と互換性です。各企業や業界が独自のシステムを開発すると、他のシステムとの連携が困難になります。
追跡技術の進化と今後の方向性
技術の進歩と社会的要請の高まりにより、製品追跡管理の未来は明るいと言えます。
IoT技術の発展により、センサーやデバイスから自動的にデータを収集し、リアルタイムで追跡情報を更新できるようになってきました。AI(人工知能)と機械学習の活用により、膨大なデータを分析し、品質問題の予兆検知や需要予測の精度向上が可能になります。
そして特に注目すべきは、製品追跡管理とESG・サステナビリティの融合です。
追跡システムがESG経営を支える重要基盤に
近年、企業経営においてESG(環境・社会・ガバナンス)への配慮が必須となっています。製品追跡の仕組みは、ESGの取り組みを実現し、証明するための強力なツールとして再評価されています。
環境面では、調達から販売までのカーボンフットプリント(温室効果ガス排出量)を可視化できます。原材料の調達から製造、輸送、販売に至るまで、各段階でのエネルギー消費や排出量を追跡することで、削減の余地を特定できます。また、循環型経済の実現においても、製品のリサイクルや再利用を促進するため、製品の素材や部品の情報を追跡することが重要です。
社会面では、人権デューデリジェンスへの対応が挙げられます。供給網における強制労働や児童労働などの人権侵害を防止することが企業の責務とされています。追跡システムを活用することで、原材料がどこで採取され、どのような労働環境で生産されたかを追跡し、人権リスクを評価できます。
ガバナンス面では、法令遵守と透明性の確保に貢献します。追跡管理の仕組みがあれば、各国の規制に対する適合性を証明する証拠を容易に提示できます。
投資家や金融機関もESG情報を重視するようになっており、製品追跡に関するデータは企業のサステナビリティ報告書における重要な情報源となります。具体的で検証可能なデータを提示することで、企業の信頼性が高まり、ESG投資の呼び込みにつながります。
また、消費者の意識変化も見逃せません。特に若い世代を中心に、倫理的消費やサステナブル消費への関心が高まっています。製品の製造過程や環境・社会への影響を知りたいという消費者のニーズに応えるために、追跡データの公開が企業の競争優位性につながります。
まとめ:デジタル時代の信頼性確保に向けて
製品追跡管理は、安全性や品質管理といった本来の役割を越えて、ESG経営の実現、ブランド価値の向上、消費者との信頼関係構築など、多面的な価値を生み出す経営戦略の重要な要素となっています。
デジタル技術の進化により、製品追跡システムの実装はより容易に、より効果的になってきました。IoT、AI、ブロックチェーンなどの先端技術を活用することで、リアルタイムでの追跡、データの改ざん防止、高度な分析が可能になっています。
トレーサビリティと同じ思想で信頼性を担保する「電子署名」
製品追跡管理が「商品やサービスの来歴を辿れるようにする」ことで信頼性を確保するように、デジタル時代にはあらゆる情報の真正性を保証する仕組みが求められています。その中核となるのが「電子署名」の考え方です。
製品追跡では、商品が供給網のどの工程を通過したかを記録することで、「いつ」「どこで」「誰が」関わったのかを証明します。電子署名も同様に、デジタル文書が「いつ」「誰によって」作成され、その後改ざんされていないかを証明する技術です。どちらも「透明性」と「検証可能性」という共通の思想に基づいています。
製造業や流通業では、品質証明書、検査成績書、原産地証明書などの文書が、取引や品質保証の重要な証拠となります。これらの文書の信頼性が担保されなければ、どれほど優れた製品追跡の仕組みを整備しても、その情報の正確性を保証できません。
従来の紙の文書やPDFファイルには、改ざんや偽造のリスクがあります。また、文書の保管や管理にもコストと手間がかかります。電子署名技術を活用することで、これらの課題を解決し、デジタル時代にふさわしい信頼性の高い文書管理を実現できます。
文書の真正性を簡単に確認できる「ONEデジDocument」
リーテックス株式会社が提供する「ONEデジDocument」の電子署名は、文書の真正性を誰でも簡単に確認できる革新的なソリューションです。
ONEデジDocumentの最大の特徴は、二次元バーコードをスマートフォンで読み取るだけで、文書の真正性を瞬時に確認できる点です。専門的な知識や特別なソフトウェアは不要で、受け取った側が簡単に文書の正当性を検証できます。
発行された文書には二次元バーコードが付与され、その文書が「いつ」「誰によって」作成されたか、その後改ざんされていないかを確実に証明できます。製品追跡システムが製造の来歴を記録するように、ONEデジDocumentは文書の来歴と完全性を保証します。
これにより、取引先との信頼関係が強化されるだけでなく、監査や法的対応の際にも、文書の真正性を明確に示すことができます。また、ペーパーレス化の推進により、文書管理のコスト削減と業務効率化も実現できます。
デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む現代において、製品だけでなく文書や情報の信頼性確保も企業の重要な責務です。ONEデジDocumentは、電子署名の考え方を活用し、企業のデジタル化と信頼性向上を同時に支援します。
詳しくは、リーテックス株式会社【公式】ONEデジDocumentをご確認ください。
製品追跡管理は、もはや一部の業界だけの課題ではなく、すべての企業が取り組むべき経営課題です。そして、製品の信頼性とともに、それを裏付ける文書の信頼性も同じく重要です。透明性の高い供給網と信頼できる情報管理を構築し、ステークホルダーからの信頼を獲得することが、企業の持続的成長の鍵となります。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。